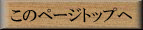JCもりやま塾
現在、JCもりやま塾による「古代米の栽培」活動は行っていません。
以下の内容は、平成22年、23年の活動紹介です。
以下の内容は、平成22年、23年の活動紹介です。
JCもりやま塾の紹介
 青年会議所(JC)は“明るい豊かな社会”の実現を目指し、次代の担い手たる責任感をもった指導者たらんとする青年の団体です。
青年会議所(JC)は“明るい豊かな社会”の実現を目指し、次代の担い手たる責任感をもった指導者たらんとする青年の団体です。
"ひとづくり"、"まちづくり"を目指していろいろな活動をしていますが、その一環として守山の子供たちを対象に「JCもりやま塾」を開いています。
子供たちが未来を目指していろいろなことを考え、実践する場を提供していますが、その一つとして下之郷史跡公園の実験田で古代米を栽培し、収穫し、試食するという年間を通じた活動を行っています。
米作りにはいろいろな経験や準備が必要となるため、「稲と雑穀の会」と共同で子供たちの指導を行っています。
平成22年度から、この活動を始めましたが、小学低学年から高学年まで50名近くの子供が参加しています。
実験田での古代米栽培風景
小学生が行う古代米栽培体験の1年間を見てみましょう。
年によって作業に少しの違いはありますが、だいたいこのような流れでお米作りを行います。
紹介する写真は「米作り作業」ばかりですが、実際には予習や作業前には青年会議所のメンバーや「稲と雑穀の会」のメンバーから、何のための作業か、何に注意するのかなどの説明もあります。
実習後にはグループに分かれて感想のまとめも行います。
年によって作業に少しの違いはありますが、だいたいこのような流れでお米作りを行います。
紹介する写真は「米作り作業」ばかりですが、実際には予習や作業前には青年会議所のメンバーや「稲と雑穀の会」のメンバーから、何のための作業か、何に注意するのかなどの説明もあります。
実習後にはグループに分かれて感想のまとめも行います。
【田植えの季節】
子供たちには初めての体験。田んぼの土の中に足を入れるのは「気持ちわるいな〜〜」。苗の植え方を習い、最初は嫌がっていた子も慣れました。一列に並んで田植えをします。

成長した苗は子供たちが 扱いやすいように小分け |

苗の植え方を学びます 弥生の人が教えてくれます |

小さい田では一列に並んで 苗を植えます |

ちょっと大きい田では二列に 並んで苗を植えます |

これだけ大勢の小学生が集まってくれました 全員でエイ!エイ!オ〜〜! |
|
【草引き】
実験田では農薬を使わないので草がよく生えます。草取りはなかなか大変な作業です。自分でやってみて米作りの大変さを実感することでしょう。

作業内容や目的を聞きます |

こっちで草引き |

あっちで草引き |

バケツ山盛りの草が何杯も |

今日の作業の感想を |

この日は看板も立てました |
【穂の観察会、鳥おどしの製作】
稲が育ってきたころ、草取りや水の管理も大切な仕事です。お米の花を観察し、現地で花の構造、受粉について学びます。
実った穂が鳥に食べられないよう「おどし」を作って、田んぼに吊るしました。

観察記録を書いてます |

こっちの田んぼはどんなんかな |

もう穂が出かけています |

保護者が作ったおどし |

子供たちが作ったおどし |

この日はおどしも付けました |
【稲刈り】
実りの秋です。古代の稲もたくさん実をつけて穂がたれさがっています。稲の刈り方を教わり、慣れない手つきで一生懸命に刈り取りました。

実をたくさんつけた古代のお米 |

鎌の使い方を聞いています |

一列に並んで一斉に稲刈り |

小さな子供もお手伝い |

大勢で稲刈りの真っ最中 |

後ろにハサ架けにした稲が見えます |
【脱穀】
ハサに架けて乾燥させた穂を脱穀します。千羽こき、立杵など昔と同じやり方での作業、なかなか大変です。棒で叩いて、古代の特徴である"のぎ"を取るのも一苦労。でも、たくさん収穫できました。

ハサに架けて乾燥したお米 |

千羽こきで籾を分離中 力がいります |

棒で叩いて"のぎ"外し |

竪杵で搗いてもみがらを外します |

機械の力も借りました |

脱穀した赤米 |
【終了式】
約半年、お米作りを体験しました。終了式に備えて赤米で飴を作りました。式当日には赤米おにぎりも作ります。米作りを指導して頂いた弥生人や関係者を招いて終了式を行いました。
お米作りの大変さと有り難さを知った「JCもりやま塾」でした。お世話をしていただいたお兄さんお姉さんありがとう!

古代米であめ作り |

皆で食べるおにぎりも赤米です |

終了式に集まった大勢の子どもたち |

弥生人に感謝状と思いでを渡します |

半年の思いを寄せ書きします |

最後に拍手で弥生人を送ります |